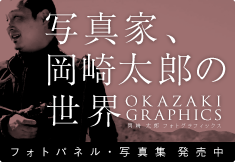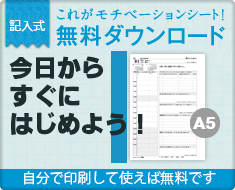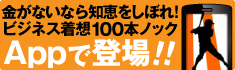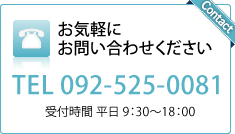気をつけなきゃいけないこと。
瞬間瞬間、口からでてくる言葉はそもそも適切ではないことが
多いわけです。文章を書き起こす場合は、何度も読み直し、文
章の流れや不足点を補えますが、話す場合はそうはいきません。
適切とは、本来伝えたい、思いや感情・考えを言葉にする際、
言葉にしようがない場合もおおく、瞬間的には適切に言葉が使
われてないことが多いのです。
言葉がそもそも持つ、制約を理解しなければいけないわけです
ね。言葉は所詮記号の集まりであり、意味付けされてるだけの
不都合なものなのです。
心の中で起きたことを正確に言葉に置き換えるのは不可能かも
しれません。
ついつい人は誇張した表現を使ってしまったり。
へんに控えめに表現してしまったり・・・・・
これに態度というか身振り・表情・声の感じ・話す速さに聞き
手は影響を受けます。紛らわされるというか・・・・
言葉からだけでは伝えきれない場の雰囲気とかその人の生命力
とかね。
本来の言葉以上に真剣さとか重たい雰囲気というのは正確に伝
わりますから・・・・・
まして、話すことが本職ではない一般人の場合、語録が少なか
ったり話なれてなかったり、組み立てが悪かったり、さまざま
な障害原因が考えられます。
また気をつけないといけないのは、単語の認識が違う場合です。
たとえば「愛」というのは、とても広義であり、どんな場合・
どういう間柄なんて条件を付加してこそ、伝え手と受け取り手の
間でようやく理解できるものでしょう。
「子供に対して」と「恋人に」と「世界」では意味がちがうで
しょ・・・・まして基準も違う、どこから「愛」でどこからは
「愛」以下とかですね。一般的には愛なんだけど・・・・
どの辺が基準なのか標準なのかなんて解りにくい。
世代や経験の違いからお互い価値観があまりにもずれてるとお話
にならない。
またこれだけ横文字カタカナ専門語がでてくると、認識間違いを
してる場合もよくあります。
以前、僕の主催のセミナーで参加者25人にコンピューター用語
10語をテストしたところ、勘違いだらけで全問不正解の社長が
いました。全問正解した人はゼロでした。
9問正解も二人・八問正解も二人と散々な結果。
問題の難しさは中だと思うんですが・・・・・
みんな解ってると思ってそれまでセミナーをしてましたから、
ゾッとしました。
ですからなるべく平易な言葉を使うことが大切。
話を戻すと、ヒアリングとは相手の内にあることを上手に引き出し
てあげる事。引き出すには同じ意味の質問を上手に角度を何回か変
えて投げることがは大切です。
その質問・回答の繰り返しの中から。。。。
導いていなければならないわけです。
なにせ話してる間にさっきいったことは間違いかななんて
思っちゃったりしますからね。
文章を書く際も、書きはじめと、書いてる最中で、より整理がつい
て、反対の結論になる場合なんかもよくあるんです。
 TEL 092-525-0081
TEL 092-525-0081