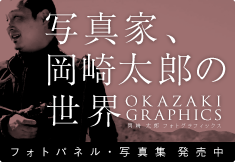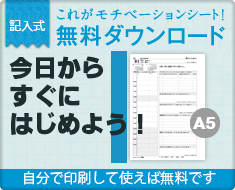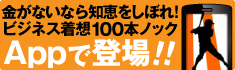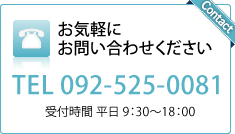|
ディフェンデイングチャンピオンのフランスが敗退。 フランスは1966年のブラジル以来はじめて予選ラウンド敗退を喫 したそうです。 |
しかも一点も一勝もあげれませんでした。
ジダンは、韓国との親善試合で肉離れをおこし、予選敗退。
もう韓国が嫌いになっちゃったでしょうね。
肉離れをおこして、まだ本調子でないジダンを使った監督の気持
ちも理解できなくはないですが・・・・ゴール前で脚がもつれて
太ももを押さえながら、転倒する場面には、リアルマドリッドの
監督は「やめてージダンを壊さないで」と叫んだのではないでし
ょうか?
あと気になるカメルーンも敗退しました。
中津江村にキャンプを張ってメディアを賑わしたチームですが
イエローカードを両チーム8枚ずつ計16枚も連発していずれも1名
欠けた10名同士の壮絶な闘いでした。
-----------------------------------------------------------
CRMって最近聞かない?次のキーワードは?
-----------------------------------------------------------
昨日はNECの担当ワカツキさんと今後の方向性をミーティング
CRMが実践できてるって、何をクリアしたらどんな基準がある
のかな?とても広いテーマだし・・・・
「当社はかくかくしかじかでCRMを実践してます」って
胸はって言えるにはどこまで構築しないといえないかな?
ただコールセンターがあるだけじゃ・・・・
CRMのソフトを導入するだけでは・・・・
当社ではCRMをやってますなんて言えないでしょ。
-----------------------------------------------------------
そもそもリレーションとは
[relation]①関係.関連のことですから
「顧客との関係をつくる」という意味です。
その関係を作るには「信頼や信用」に昇華させるためには
一定間隔で複数回のコミュニケーションを積んでいかないと築け
ないし・・たった1回の応対では築けるはずも無いですよね。
だから正確には1回目の購入時点においては、関係作りの第一歩
を踏み出しただけで、まだまだ大切な関係はまだ作れてはいない
んですね。
しかしこの第一歩からCRMがはじまるんです。
しかし「第一歩の踏み方が各企業で違うはず」だと思うんです。
つまり同じじゃない。同じはずが無い。
目的に左右されるはずですもんね。
つまり将来のCRMを実践してる青写真が必用です。
顧客との磐石な関係が構築できた場合、どういうイメージになっ
てどう利益に貢献してるかのイメージをつくらないと、CRMの
設計が出来ないわけです。
そもそも全ての顧客とCRMをして関係を作る場合もあるだろう
し、ある企業の場合,ある一定以上の優良顧客を対象にはじめる
かもしれないし・・・・・はたまた・・・・・・・
顧客の構成や商品構成や特性や属性やサービスや会社の考え方で
コミュニケーションの頻度やタイミングや使うツールも違って
当然な訳ですから・・・・
-----------------------------------------------------------
そして骨子がまとまって、改めて見てみるとそれがワントゥワン
的だったり、そうじゃなかったりするかもしれませんが、それは
どちらでもいい訳です。
すべての企業がワントゥワンマーケティングを活用せねばならな
いなんてことは無いわけですから・・・・・
まず自社の進みたい方向があって、その方向に行くために有効で
あれば使えばいいし、参考にすればいいわけで・・・・
まず先に手法や他人の考えを知る事で、左右されるのはおかしい
ですよね。
所詮、書籍や先生は、現場への落とし方を教えてはくれません。
また時代は刻々と変化していて普遍の手法なんてありえません。
今でも新しい手法が開発され、古い手法が見直されたり、改善さ
れたり・・・・どの手法が最適かは誰にも判断できないわけです
大切なのは、手法を実践することが目的ではなく、本当の目的を
実現することであり、その目的がはっきりしていなければ、どこ
に進めればいいのかさえ見失ってしまいます。
けして方法はひとつではありません。
そして絶対もありません。かならず他の方法があるはずです。
少し条件がかわれば、環境が変れば、未来は変化します。
一寸先は誰にもわかりません。
-----------------------------------------------------------
柔軟な足腰で変化に対応出来る事が大切です。
コンピューターメーカーの作る英語三文字に翻弄されるのは
止めにしませんか?
 TEL 092-525-0081
TEL 092-525-0081